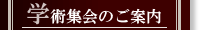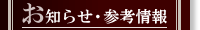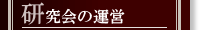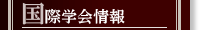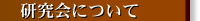
あゆみ
設立の経緯とその後の展開
肝類洞壁細胞研究会の設立者である谷川久一先生にお聞きした内容をもとに、
設立の経緯とこれまでの取り組み、今後の展望等についてご紹介させていただきます。

設立の経緯
ヒト肝臓の生検標本、特に、肝内胆汁うっ滞症の電顕観察を大学院生の頃から取り組んでおられた谷川久一先生は、
伊藤俊夫先生が精力的に研究されていたIto細胞を主とする肝類洞壁細胞に興味を抱かれ1965年に
「Fine Structure of the Reticuloendothelial Cells in the Normal Rat Liver: Morphological Classification」を
The Kurume Medical Journal (vol.12, No.3, p137-147)に記されました。また、「Ultrastructural Aspect of The Liver and Its Disorders」を
医学書院 (Springer)から英語(1968年)、イタリア語(1968年)、スペイン語(1971年)の3カ国語で出版されました。
これらの業績が海外の研究者の目に留まり1973年10月にドイツ、フライブルグで行われた国際会議で、電顕観察によるとコラーゲンが Disse腔に沈着していることが判るのでfat-storing cellがコラーゲンを産生するのではないかとの可能性を講演されました。
この発表は参加していた世界の研究者から批判されましたが、Hans Popper教授からは賞賛を受けられたそうです (「Collagen Metabolism in the Liver」というProceedingが出版された)。 その後、1977年にEddie Wisse教授が世界中の研究者に声をかけ「International Symposium on Cells of the Hepatic Sinusoid(第1回目)」が The NetherlandsのNoordwijkerhoutで開催されました。44歳で教授に就任直後の谷川久一先生は突然講演の依頼を受け取られて参加することになりました。 この場には、やはりHans Popper教授も招かれていました。その当時は世界的にもまだ肝類洞壁細胞に関する研究は始まったばかりでした。
このような海外での動きに同調して日本国内でも肝類洞壁細胞に関する研究が盛んになってきました。
1984年の第20回日本肝臓学会(会長 森亘)では「肝類洞壁細胞の形態と機能」というシンポジウムが企画され、 谷川久一先生、浪久利彦先生が司会でKupffer細胞、内皮細胞、伊東細胞、pit細胞などに関する16講演がなされました。
また、1986年の第72回日本消化器病学会総会(会長 市田文弘)では、谷川久一先生が「肝疾患と肝類洞壁細胞」の特別講演をされました。 この講演は多くの研究者から賞賛を受けられたとのことです。
このような背景を基に、市田文弘先生の勧めで、また、谷川久一先生が教授就任後10年になられたことを機会に、 浪久利彦先生、和気健二郎先生らが企画に参加されて日本における第1回肝類洞壁細胞研究会が久留米の地で開催されることになりました(1987年12月14日)。 当時、臨床の医師が基礎的研究を発表する機会が少なかったことや、臨床上の疑問点を基礎の専門家と議論する研究会が無かったこともあり、 忘年会を兼ねて熱い議論をする研究会が立ち上がったことで注目を集めたわけです。
これらの業績が海外の研究者の目に留まり1973年10月にドイツ、フライブルグで行われた国際会議で、電顕観察によるとコラーゲンが Disse腔に沈着していることが判るのでfat-storing cellがコラーゲンを産生するのではないかとの可能性を講演されました。
この発表は参加していた世界の研究者から批判されましたが、Hans Popper教授からは賞賛を受けられたそうです (「Collagen Metabolism in the Liver」というProceedingが出版された)。 その後、1977年にEddie Wisse教授が世界中の研究者に声をかけ「International Symposium on Cells of the Hepatic Sinusoid(第1回目)」が The NetherlandsのNoordwijkerhoutで開催されました。44歳で教授に就任直後の谷川久一先生は突然講演の依頼を受け取られて参加することになりました。 この場には、やはりHans Popper教授も招かれていました。その当時は世界的にもまだ肝類洞壁細胞に関する研究は始まったばかりでした。
このような海外での動きに同調して日本国内でも肝類洞壁細胞に関する研究が盛んになってきました。
1984年の第20回日本肝臓学会(会長 森亘)では「肝類洞壁細胞の形態と機能」というシンポジウムが企画され、 谷川久一先生、浪久利彦先生が司会でKupffer細胞、内皮細胞、伊東細胞、pit細胞などに関する16講演がなされました。
また、1986年の第72回日本消化器病学会総会(会長 市田文弘)では、谷川久一先生が「肝疾患と肝類洞壁細胞」の特別講演をされました。 この講演は多くの研究者から賞賛を受けられたとのことです。
このような背景を基に、市田文弘先生の勧めで、また、谷川久一先生が教授就任後10年になられたことを機会に、 浪久利彦先生、和気健二郎先生らが企画に参加されて日本における第1回肝類洞壁細胞研究会が久留米の地で開催されることになりました(1987年12月14日)。 当時、臨床の医師が基礎的研究を発表する機会が少なかったことや、臨床上の疑問点を基礎の専門家と議論する研究会が無かったこともあり、 忘年会を兼ねて熱い議論をする研究会が立ち上がったことで注目を集めたわけです。
これまでの取り組み、今後の展望
第1回目の会はクローズドの会だったと認識されている方も多いとは思いますが、実はそうではなく、
谷川久一先生から招待状を送られた先生が参加し、類洞壁細胞に関する総論を発表する形式でした(参加者35名)。
場所は第11回まで久留米萃香園ホテルでした。
第2回目以降は開催を広告し、演題を募集することで参加者が増加しました。 いつも年末に行われ、激しい議論の後、忘年会を兼ねた懇親会がある研究会形式でした。
第2回目はEddie Wisse教授、第3回目はKarl Decker教授、 第4回目はAlbert Geerts教授、また、第11回目はEddie Wisse教授、Don Rockey教授が 海外からの特別講演者として招かれました。 演題数が最も多かったのは第8回(1994年12月15-16日)で65演題、参加者141人でした。
参加者が最も多かったのは第7回(1993年12月16-17日)で182人でした。 参加者が増えた原因を谷川久一先生ご自身は判らないと仰っておられますが、 肝臓の基礎と臨床を共に研究する者としては忘年会を兼ねた久留米詣でが年末行事になっていたことが推測されます。
この間、第10回まで記録誌「肝類洞細胞研究の進歩」が毎回出版され、第11回の記念研究会では「Liver Disease and Hepatic Sinusoidal Cells」という英文誌が出版されました。
第11回肝類洞壁細胞研究会の世話人会の席上で、谷川久一先生が退官されるに伴い研究会の存続が話題になりました。
谷川久一先生ご自身は閉会されることもお考えになられていたようですが、市田文弘先生の強い勧めで継続することが了解され、 当番世話人の持ち回りで研究会が継続されることになりました。
これに伴い第12回の研究会は市田隆文先生と内藤真先生のお世話により 新潟市で(1998年12月17-18日)、第13回の研究会は沖田極先生のお世話により宇部市で(1999年12月17-18日)と続き現在までに第24回が終了しました。
参加者が少ない時期もありましたが、近年、免疫担当細胞や自然免疫に関する発表なども増え、 再び充実してきた感があります。
肝類洞壁細胞研究会の特徴は、肝臓を主とする臨床医と形態学、病理学、生化学、免疫学などの基礎の研究者が 共に集い、議論し、夜は懇親を深めるというスタイルを貫いてきたところにあると考えられます。
参加研究者は非常に熱心であり、本研究会で活躍された先生の中から多数、教授になられた先生がおられることからも本研究会のレベルの高さが判ります。 今後も将来の日本の肝臓学のリーダーを育てる研究会であることが重要です。また、本研究会は肝細胞と脾臓、膵臓、消化管などの他臓器と血管を通して情報交換する 類洞を構成する細胞群を研究対象にしており、臓器相関を研究する上で重要です。肝臓を代謝組織と見る上で肝類洞壁細胞の研究をさらに発展させることが必要です。
谷川久一先生は、本分野の研究を志す若い研究者には、肝臓と周辺臓器との相関を考える起点として肝類洞を考えて欲しいと言われています。
谷川久一先生は最近、本屋さんへ行くと肝臓の本が書棚に極めて少なくなっていることに気がつかれ、嘆かれています。 以前は、医学書の中に肝臓関係の本がたくさん置いてあったが、今は数冊が置いてあるだけで、これが肝臓研究の状況を表していると指摘されています。
後世に記録を残す努力をこの研究会を通じて高めたいものです。
第2回目以降は開催を広告し、演題を募集することで参加者が増加しました。 いつも年末に行われ、激しい議論の後、忘年会を兼ねた懇親会がある研究会形式でした。
第2回目はEddie Wisse教授、第3回目はKarl Decker教授、 第4回目はAlbert Geerts教授、また、第11回目はEddie Wisse教授、Don Rockey教授が 海外からの特別講演者として招かれました。 演題数が最も多かったのは第8回(1994年12月15-16日)で65演題、参加者141人でした。
参加者が最も多かったのは第7回(1993年12月16-17日)で182人でした。 参加者が増えた原因を谷川久一先生ご自身は判らないと仰っておられますが、 肝臓の基礎と臨床を共に研究する者としては忘年会を兼ねた久留米詣でが年末行事になっていたことが推測されます。
この間、第10回まで記録誌「肝類洞細胞研究の進歩」が毎回出版され、第11回の記念研究会では「Liver Disease and Hepatic Sinusoidal Cells」という英文誌が出版されました。
第11回肝類洞壁細胞研究会の世話人会の席上で、谷川久一先生が退官されるに伴い研究会の存続が話題になりました。
谷川久一先生ご自身は閉会されることもお考えになられていたようですが、市田文弘先生の強い勧めで継続することが了解され、 当番世話人の持ち回りで研究会が継続されることになりました。
これに伴い第12回の研究会は市田隆文先生と内藤真先生のお世話により 新潟市で(1998年12月17-18日)、第13回の研究会は沖田極先生のお世話により宇部市で(1999年12月17-18日)と続き現在までに第24回が終了しました。
参加者が少ない時期もありましたが、近年、免疫担当細胞や自然免疫に関する発表なども増え、 再び充実してきた感があります。
肝類洞壁細胞研究会の特徴は、肝臓を主とする臨床医と形態学、病理学、生化学、免疫学などの基礎の研究者が 共に集い、議論し、夜は懇親を深めるというスタイルを貫いてきたところにあると考えられます。
参加研究者は非常に熱心であり、本研究会で活躍された先生の中から多数、教授になられた先生がおられることからも本研究会のレベルの高さが判ります。 今後も将来の日本の肝臓学のリーダーを育てる研究会であることが重要です。また、本研究会は肝細胞と脾臓、膵臓、消化管などの他臓器と血管を通して情報交換する 類洞を構成する細胞群を研究対象にしており、臓器相関を研究する上で重要です。肝臓を代謝組織と見る上で肝類洞壁細胞の研究をさらに発展させることが必要です。
谷川久一先生は、本分野の研究を志す若い研究者には、肝臓と周辺臓器との相関を考える起点として肝類洞を考えて欲しいと言われています。
谷川久一先生は最近、本屋さんへ行くと肝臓の本が書棚に極めて少なくなっていることに気がつかれ、嘆かれています。 以前は、医学書の中に肝臓関係の本がたくさん置いてあったが、今は数冊が置いてあるだけで、これが肝臓研究の状況を表していると指摘されています。
後世に記録を残す努力をこの研究会を通じて高めたいものです。
(文責 河田則文)