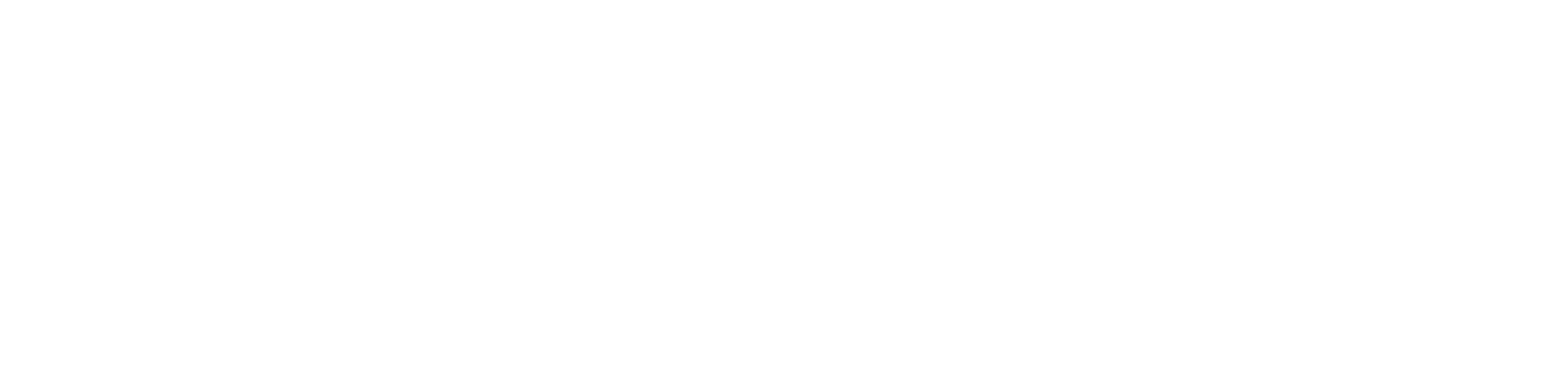message 代表からのご挨拶
代表世話人挨拶

2025年1月より河田則文先生の後任として肝類洞壁細胞研究会の代表世話人に就任いたしました。本会は初代代表世話人である故谷川久一先生のもと、故市田文弘先生、故浪久利彦先生、故高田昭先生らが集い、1987年12月に発足した伝統ある研究会であり、渡辺純夫先生、河田則文先生に次いで私が第四代目の代表世話人にあたります。微力ながら本研究会のさらなる発展に尽くす所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。
肝臓は全身の代謝の要として、消化器系臓器の中でも特異な役割を担っていますが、その多彩な機能は肝実質細胞とそれを取り巻く種々の肝類洞壁細胞の巧妙な協調によって成り立っています。従って、肝臓の生理的機能や病態を正確に理解するには、これらの肝構成細胞の個々の形態や機能に加えて、各細胞群による組織構築や細胞間の相互作用など、様々な観点からの詳細な研究が不可欠です。本研究会が発足した当初は、肝星細胞が肝線維化における主要なマトリックス産生細胞であることがようやく明らかにされつつあった頃で、またKupffer細胞をはじめとする肝内免疫細胞が肝病態に果たす役割も注目され始めた、言わば肝類洞壁細胞研究の黎明期でした。肝類洞壁細胞の研究には、形態学的観察に加えて細胞単離培養技術の確立に伴う細胞生物学的解析が不可欠で、その発展普及に初期の本研究会が果たした役割は極めて大きかったと言えます。さらに近年では様々な分子生物学的手法やオミックス解析、シングルセル解析などを用いた次世代型の研究が次々と繰り広げられています。肝臓病学の関心事もウイルス肝炎から代謝機能障害関連の脂肪性肝疾患へとパラダイムシフトが生じてきていますが、進行した肝線維症に対する抗線維化治療や、肝不全に対する再生医療、肝癌の免疫病態に対するアプローチなど、未だ解決していない大命題にはいずれも肝類洞壁細胞が深く関わっており、さらなる研究が求められます。
本研究会はその発足当初から、海外の研究者との交流や情報交換も盛んに行われてきており、留学経験や共同研究を通じて国際的な研究活動を展開されている会員も枚挙に暇がありません。肝類洞壁細胞国際シンポジウム(International Symposium on Cells of Hepatic Sinusoid)とも連携しており、わが国でも過去3回開催されていますが、2028年には15年ぶりに再び第24回の本国際シンポジウム(the Liver Sinusoid Meeting)を東京に誘致して開催することが決定しております。このような国際交流を弛まず続けることにより、国際性豊かでかつ競争力のある研究者を育成していくことも、本研究会の重要な使命の一つです。本研究会の活動を通じて、基礎系・臨床系の両面から肝臓の生理的機能および病態の一層深い理解が得られるようになり、肝臓病学のアンメットニーズに応えられるような研究が育まれることを大いに期待します。
肝類洞壁細胞研究会代表世話人
順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学教授
池嶋健一